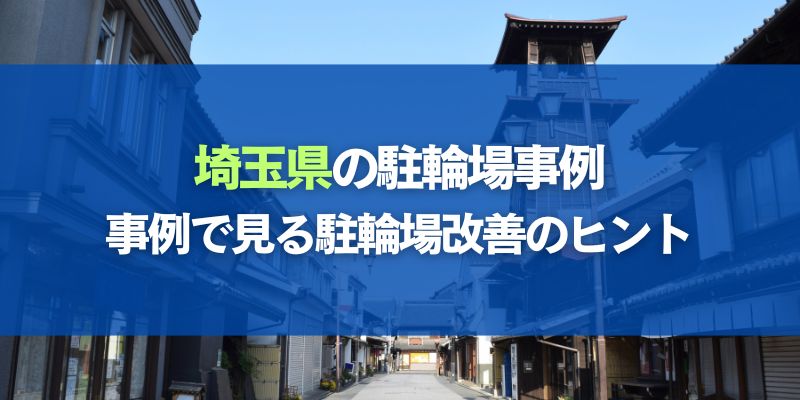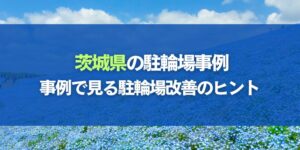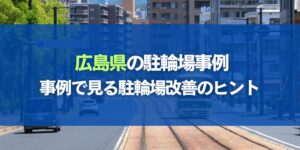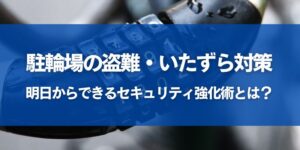『自転車の県』埼玉ならではの駐輪場事情
埼玉県といえば、実は全国でもトップクラスの「自転車県」だということをご存知でしょうか。
総務省統計局の全国消費実態調査などのデータを見ると、1世帯あたりの自転車保有台数が全国平均を大きく上回っています。
埼玉はJRや私鉄などの鉄道網が発達しているため、多くの方が「自宅から駅まで」のラストワンマイルで自転車を愛用しているのが理由のひとつです。朝の通勤ラッシュ時に駅周辺で見かける自転車の多さは、まさに埼玉らしい風景といえます。
加えて、県内では中高生の自転車通学も盛んです。学校や学校周辺の駐輪場には朝夕びっしりと自転車が並びます。
実際、さいたま市などでは条例によって、一定規模以上の商業施設や建物に駐輪場の設置を義務付けています(附置義務)。これは行政が「必要だから」設けたルールで、地域の実情をよく表しています。
そこで今回は、埼玉県内で実際に行われた駐輪場の改善事例をいくつかご紹介します。
埼玉県の駐輪場改善事例
事例① 大和田駅南自転車駐車場(駐輪ラック57台設置、コンベア2基)

地上三階建ての大和田駅南自転車駐車場では、コンベア2基を設置しています。駅周辺の公共駐輪場では、通勤・通学ラッシュ時の利用が集中するため、スムーズな出し入れができる環境づくりが重要です。
コンベア設備により、2階への階層移動が楽になり、電動アシスト自転車のような重い自転車でも負担なく利用できるようになりました。年齢を問わず多くの方が利用する公共施設では、このようなバリアフリー対応が利用者の満足度向上につながっています。
事例② 土呂駅西口自転車駐車場(駐輪ラック210台、コンベア1基)

地上二階建ての土呂駅西口自転車駐車場は、駐輪ラックの大規模な入換とコンベア1基を効果的に配置しました。大規模な駐輪場では、台数を確保するだけでなく、利用者の動線設計も重要な要素となります。
適切な配置により、朝夕の混雑時間帯でも利用者がスムーズに自転車を出し入れできる環境が整備されています。大容量駐輪場を計画する際の参考となる事例です。
事例③ 東松山市立南中学校(駐輪ラック70台)

東松山市立南中学校では、中学生の利用特性に配慮した整備が行われました。学校の駐輪場では、生徒が毎日利用することを前提とした耐久性の確保と、整理整頓しやすいレイアウト設計が重要になります。
駐輪ラックの配置を工夫することで、生徒が自然と整理して駐輪しやすい環境を作り出しています。また、成長期の生徒が長期間使用することを考慮し、安全で頑丈な構造となっています。
事例④ みずほ銀行浦和支店新店舗(駐輪ラック25台)

みずほ銀行浦和支店の新店舗では、25台規模の駐輪場が設置されています。金融機関という性格上、建物の外観に調和したデザイン性と、来店客が利用しやすい機能性の両立が求められました。
銀行らしい落ち着いた外観を保ちながら、お客さまが気軽に利用できる駐輪環境を実現しています。商業施設における駐輪場の計画時に参考となる事例です。
事例⑤ 藤和シティホームズ武蔵浦和(駐輪ラック17台)

藤和シティホームズ武蔵浦和では、駐輪場において、マンション住民の日常利用に配慮した設計が採用されています。集合住宅では、住民の利便性と建物全体の景観との調和が重要な要素となります。
雨風からの保護機能を持ちながら、スペースを有効活用できる二段式駐輪ラックを設置し、集合住宅における駐輪場整備代表的な事例となっています。
埼玉の駐輪場計画で、特に考慮したい3つの視点
利用者の「属性」を深く考える
駐輪場を計画するときに一番大切なのは、「誰が、どんなふうに使うのか」をしっかり考えることです。
例えば通勤利用の方は、朝の忙しい時間に「サッと置いて、サッと取り出したい」と思っています。一方、通学利用の学生さんは比較的時間に余裕があるものの、「盗まれたら困る」「壊されたくない」という心配が大きいかもしれません。
子育て中のファミリー層は、子供乗せ自転車や電動アシスト自転車を使うことが多く、普通の自転車より重たくて幅も取ります。ご高齢の方が多い地域なら、重い自転車を持ち上げるのは大変ですから、できるだけ楽に使える工夫が喜ばれます。
このように、使う人によって「あったらいいな」と思うポイントがまったく違うんです。だからこそ、最初にしっかりと利用者のことを考えることが、成功する駐輪場づくりの第一歩になります。
埼玉県や各市町村の「ルール」を事前に確認する
埼玉県内で駐輪場を作るときは、各市町村で決められているルールを最初に確認しておくことが大切です。
例えば、さいたま市には「自転車等の放置の防止に関する条例」があり、一定の大きさ以上の建物を建てるときは、駐輪場を必ず作らなければいけません(附置義務)。「あとから知って慌てた」ということがないよう、建物の用途や規模に応じて何台分必要なのか、どんな構造にすべきなのかを事前に調べておくと安心です。
他の市町村でも似たようなルールがある場合があります。「知らなかった」では済まされませんから、計画の初期段階で役所の担当部署に相談してみることをおすすめします。最初に確認しておけば、後々困ることもありませんからね。
安全な利用環境と防犯対策
自転車をたくさん使う埼玉県では、駐輪場での安全対策と防犯対策がとても重要です。
見通しの良いレイアウトは、利用者同士がぶつからないようにするだけでなく、不審な人が近づきにくい効果もあります。夜でも安心して使えるよう適切な場所に照明を付けることで、盗難などの心配も減らせます。
防犯カメラの設置や、管理する方による定期的な見回りなど、設備面と運用面の両方で対策を考えることで、より安心して使える駐輪場になります。
特に駅周辺や商業施設では色々な人が利用するので、「安心して使える場所だな」と感じてもらえることがとても大切です。
おわりに
公共施設では大容量とバリアフリー、学校では安全性と使いやすさ、民間施設では見た目と機能性の両立—それぞれの特徴に合わせた工夫がされていました。
また、利用者をしっかり分析すること、自治体のルールを確認すること、安全・防犯に配慮すること。この3つの視点は、どんな駐輪場を考える場合でも大切なポイントになります。
駐輪場の計画は、建築のこと、交通のこと、防犯のこと、景観のことなど、実に様々な専門知識が必要になる分野です。「もっと良い駐輪場にしたいけれど、どうしたらいいかな?」と思ったときは、専門業者に相談してみると、地域の実情に合った良いアイデアがもらえます。
 ヨコトクくん
ヨコトクくん駐輪場のことでお困り事やわからないことがありましたら何なりと私たちヨコトクにもご相談ください。