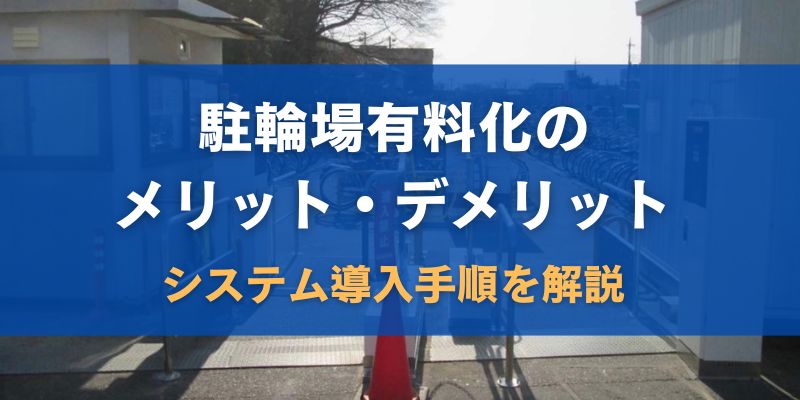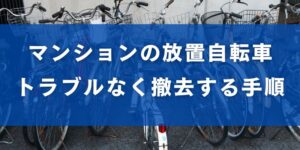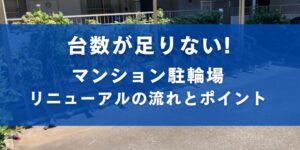こんにちは。駐輪場の何でも屋、ヨコトクです。
ヨコトクでは、「無料駐輪場の有料化」について相談を受けることがあります。
マンションや商業施設、公共施設にある無料駐輪場は、気軽に利用できありがたい反面、管理者にとってはトラブルや問題が起こりやすい場所です。
自転車が乱雑に置かれ通路をふさいでいたり、明らかに使用されていない自転車が長期間放置されていたりと、多くの施設で無料駐輪場の管理が課題となります。
これらの問題は、単に見た目の悪さだけでなく、安全性の低下や管理コストの増加などにつながります。
そこで検討されているのが、無料駐輪場の有料化という解決策です。
今回は、駐輪場を有料化することのメリットとデメリット、そして具体的な導入手順について詳しく解説します。
駐輪場の有料化は、一見、利用者の反発を招きそうに思えるかもしれません。
しかし、適切に導入することで、施設の美観維持、利用者のマナー向上、そして管理の効率化など、多くのメリットをもたらしてくれます。
この記事を通じて、駐輪場有料化の全体像を把握し、皆さまの施設に最適な解決策を見出すための一助となれば幸いです。それでは、駐輪場有料化のメリットから詳しく見ていきましょう。
駐輪場を有料化するメリット
駐輪場を有料にすると、利用者から不満がでることを心配されるのではないでしょうか。
しかし、駐輪場有料化には多くのメリットがあります。
1. 駐輪場が自然と整理される
まず、有料化することでほとんどの場合、放置自転車が極端に少なくなります。
また、有料化と合わせて、駐輪区画の整理や、駐輪ラックを設置することで煩雑な駐輪のされ方もなくなります。
結果的に、通路にはみ出す自転車などもなくなるので、お子様や高齢者の方、車椅子の方などの安全も確保されます。
2.お店や公共施設の利用者の満足度が上がる
有料化することで、その施設を利用する目的以外での駐輪を減らすことも可能です。
特に、駅周辺の商業施設・公共施設では、お出かけや通勤・通学目的の方による駐輪場の不正利用が頻繁に起こります。
店舗・施設の利用者のために、短時間の駐輪は無料、長時間の駐輪は有料といった切り分けを行うことで、そのような不正利用は起こりにくくなります。
結果的に、施設の本来の利用者(お客様、従業員)のための駐輪スペースを確保しやすくなり満足度が向上します。
3. 管理費用の削減と収入源の確保
駐輪場の整理が自然と行われることで、今まで整備にかけていた管理費用を削減することができます。
また利用料を財源として、設備のメンテナンスやグレードアップにかかる費用を補填することも可能です。
例えば、マンションの駐輪場であれば老朽化した屋根を修理したり、防犯カメラを設置することなども考えられます。
このように、駐輪場の有料化には様々なメリットがあります。ただし、これらのメリットを実現するためには、十分な計画と利用者への丁寧な説明が必要です。
次は、有料化する際のデメリットや注意点についてもみていきましょう。
駐輪場を有料化する主なデメリット
駐輪場の有料化を検討する際、特に注意すべき2つのデメリットがあります。
1. システム導入が必要な場合、初期コストがかかる
駐輪場を有料化する際には、必要な設備やシステムの導入に伴う初期コストが発生します。
特に精算機に関しては高額になるケースが多いです。
またそれに伴い電源工事や機器の設置場所など既存の駐輪場自体の改修工事が必要になる可能性があります。
ヨコトクが提供する無人駐輪場システムのスマチューは高額な精算機を必要としないので20台に満たない小規模駐輪場であったとしても、導入が可能です。
詳細はこちらのページも御覧ください。
2. 近隣で路上駐輪が増加する可能性
駐輪場を有料化することにより、ルールを守らない利用者により歩道や路上など、駐輪場外の本来駐輪が禁止されている場所への不法駐輪が増加するリスクがあります。
路上駐輪の増加は、歩行者や車両の通行を妨げたり、街の美観を損ねることにつながります。
そのため、路上駐輪禁止の掲示や、行政と連携した撤去作業などを後々検討する必要がでてくる可能性があります。
メリットばかりではない駐輪場の有料化ですが、事前にデメリットを理解しておくことがリスクを減らすことにつながります。
それでは、続いて有料化の具体的な流れをみていきましょう。
駐輪場の有料化の手順
施設や駐輪場の規模によって変わることもありますが、駐輪場を有料化する際の流れは概ね以下のとおりです。
1. 現状を調査し問題点を明確にする
まずは、現在の駐輪場の利用状況を調査します(利用率、ピーク時間、長期駐輪の割合、チャイルドシート付きの電動アシスト自転車の割合など)。
そのうえで、現在抱えている問題点(放置自転車、スペース不足、管理コストなど)を明確にします。
2. 専門家を交えて駐輪場有料化が問題解決につながりそうかを最終確認
現状を確認したうえで、駐輪場システムの導入実績のある業者を交えて、有料化が問題解決につながるかを最終確認しましょう。
このまま有料化を進めることが決定したら、大まかな見積もりも同時にとっておくと今後の予算確保などがスムーズになります。
3.料金体系・運営方式の決定
予算確保には、収支計画もある程度たてておく必要があります。周辺の駐輪場の料金などを参考に、適切な料金を設定します。
商業施設、公共施設などの場合は、店舗利用者むけの短時間無料時間を決めたり、定期利用者向けの割引プランや、施設との連携による割引制度なども考慮します。
マンション駐輪場の場合は、一般的な相場から住人に許容される範囲の料金を検討します。
マンションの場合、月額300円〜500円程度を年払いで徴収してしまうことが比較的多くなります。
加えて、無人化システム、有人管理、またはその併用などの運営方式や、料金徴収システムの種類(自動精算機、ICカード、スマートフォンアプリなど)を選択します。
これらを決めることで、収支計画をたてることが可能になります。
4.収支計画の作成と予算確保
料金や運営方式、システムの種類などが決まると、必要な経費と得られる収益の目処がたちますので、その情報をもとに収支計画をたてます。
同時に業者から正確な初期投資額(設備導入、工事費用など)を出してもらい予算を確保します。
運営コストと予想収益を試算し、中長期的な収支計画を立てます。
必要に応じて、行政からの補助金や融資の活用を検討します。
5.導入スケジュールの策定
システム導入から本格運用までの具体的なスケジュールもきちんと作成しましょう。
基本的には施工を依頼している業者からスケジュールが提出されるはずです。
必要に応じて、段階的な導入(一部エリアでの試験運用など)を計画します。
6. 広報活動の実施
スケジュールが確定したら、施設の利用者や、マンション住人など、駐輪場利用者に向けた告知を行います。
告知には、駐輪場への掲示、ホームページ、DM、メーリングリスト、公式LINEなど利用します。
有料化が始まる具体的な日付や、それに伴う駐輪場工事の期間など明確に伝えましょう。
単に、有料化することだけなく、その目的や意義も含めて説明することで利用者から同意を得られるようになります。
7.駐輪場工事の開始
有料化のためのシステムの設置や新しい駐輪ラックの設置など必要な工事を開始します。
工事期間中の駐輪場所など利用者への対応も忘れずに行います。
8. 運用開始改善
工事が完了したらいよいよ運用開始です。定期的に利用状況や収支をチェックしましょう。
利用者アンケートなどを実施し、満足度や改善要望を把握することも効果的です。
施工業者と連携して、機器の定期的なメンテナンスも実施することで、トラブルを予防することができます。
上記のような手順を踏むことで、スムーズな有料化の実現と、利用者の理解を得やすくなります。
駐輪場システムの種類と選び方の基準
有料の駐輪場を運営するには、管理のためのシステムが必要です。
ここでは、システムの種類と特徴と、その選定基準について解説します。
主に駐輪場を有料化する際のシステム管理方法は下記の3種類に分けられます。
- 1.駐輪ラックごとの電磁ロックと精算機を設置する方式(中規模駐輪場)
- 2.駐輪ラックごとの電磁ロックではなくゲートで入退場と精算を管理する方式(大規模駐輪場)
- 3.駐輪ラックごとの電磁ロックとスマホ決済で精算機を設置しない方式(小規模駐輪場)
駐輪場によっては上記を併用するようなパターンもありますが、それぞれの特徴について解説していきます。

現在、スーパーなど商業施設や、公共施設で最もみかけることが多いシステムです。
駐輪ラックごとにロック機能がついており、規定の時間を超えるとロックを外すために精算機で料金を支払う方式です。自転車ごとに個別で駐輪時間の管理がしやすく便利です。
・向いている駐輪場:中規模な駐輪場
・注意点:
自転車を駐輪ラックに浅めに停めることで、ロックをかけずに長時間駐輪するというマナー違反者が一定数現れる可能性があります。場合によっては、定期的に見回りを行う人員を用意したりと別のコストが必要になる場合があります。

ゲートで駐輪場利用者の入退場や精算を一括で管理する方式です。駐輪ラックごとの電磁ロックが必要なくなるので、台数が多い駐輪場の場合、電磁ロックと精算機を複数台設置するよりもコストが抑えられることがあります。
・向いている駐輪場:駐輪台数が多く、延床面積の広い大規模な駐輪場
※月極定期利用と一時利用の併用にも対応しています。
※バイクと自転車を判別し異なる料金設定を行うことも可能です。
・注意点:
入退場のピーク時間帯に渋滞することや、発券式の場合、一時利用者が券をなくしてしまうことや、機械の券づまりなどのトラブルが起こり得ます。その際の、問い合わせ窓口や対応できる管理者が必要になります。
精算機もゲートも設置せず、駐輪ラックごとの電磁ロックと紐づけ、キャッシュレス決済を行う方式です。スマートフォン上で、クレジットカードやPayPay・楽天ペイなど各種決済サービスを利用し、決済を行います。高額な精算機や集金にかかる管理人件費が発生しないため、小規模な駐輪場でも収益化が可能です。弊社ヨコトクが開発したスマチューというシステムがこれに当たります。LINEの画面から駐輪ラックの施錠・解錠が可能です。

・向いている駐輪場:小規模な駐輪場、もしくはキャッシュレス専用エリアを設けたい大中規模駐輪場
※精算機などを設置すると採算が合わない場所や、ビルやマンションの一角など今まで利用されずにいたスペースでも利用可能です。
・注意点:
現金での支払いに対応していないため、スマホでの操作に苦手意識がある利用者には受け入れられない可能性があります。その場合、駐輪場の一部をスマートフォン決済のエリア、一部を精算機を用いた現金精算用のエリアにするなどして、必要な精算機の台数を減らすために導入頂くことも可能です。
まとめ
駐輪場の有料化は、多くの施設が直面している駐輪問題に対する有効な解決策の一つです。今回は、有料化のメリット、デメリット、導入手順、注意点について詳しく説明してきました。
有料化を適切に実施することは、より良い駐輪環境を作り、施設全体の価値向上につながっていきます。
有料化や駐輪システムの導入を検討している方は、この記事を是非参考にしてください。
不明点があれば、駐輪場の何でも屋ヨコトクが皆様の駐輪場に関するお悩みを必ず解決させていただきますのでいつでもご相談ください。